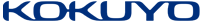リサーチ
2019.12.02
望まぬ転勤に廃止の動き。家庭内事情等への配慮も
軽視できない、転勤によって生じるさまざまな困難

2016年、独立行政法人 労働政策研究・研修機構によって、『企業の転勤の実態に関する調査』が行われた。この調査は、厚生労働省雇用環境・均等局が要請した課題研究の一環として行われたものである。企業10,000社と正社員80,000人の回答から、既存の転勤制度が持つさまざまな問題や、今後の解決策について考察する。
<調査対象>
企業調査が全国の常用労働者300人以上の企業10,000社
正社員調査が調査対象企業で転勤経験のある正社員8人に配付(計80,000人)
<有効回答数>
企業調査:1,852件(有効回収率:18.5%)、正社員調査(転勤経験者):5,827件(有効回収率:7.3%
独立行政法人 労働政策研究・研修機構による『企業の転勤の実態に関する調査』の企業調査で、正社員(総合職)の転勤(転居を伴う配置転換)がどのくらいあるかをたずねたところ、「正社員(総合職)のほとんどが転勤の可能性がある)」が33.7%で1位、「正社員(総合職)でも転勤をする者の範囲は限られている」(27.5%)、「転勤はほとんどない(転勤が必要な事業所がない)」(27.1%)であった。正社員数の多い大企業になるほど、全国に支社や支店を持つ企業が多くなるためか、「正社員(総合職)のほとんどが転勤の可能性がある」と回答する割合が高くなる。
転勤の目的としては、「社員の人材育成」が66.4%で最多、他には「社員の処遇・適材適所」、「組織運営上の人事ローテーションの結果」、「組織の活性化・社員への刺激」等が挙げられた。
転勤命令の決定方法を「A:会社主導ですべて決定」と「B:社員の意見・希望を踏まえて決められている」の2択で問うと、79.7%が「Aに近い・Aにやや近い」と回答している。8割弱の企業において、本人の意思よりも会社主導で転勤が決定されていることがわかる。
では、転勤をする本人はどのように感じているのだろうか。「転勤があることにより、困難に感じること」で、「そう思う」と「ややそう思う」の合計が最も多かったのは、「介護がしづらい(75.1%)」であった。そして、「持ち家を所有しづらい(68.1%)」、「進学期の子どもの教育が難しい(65.8%)」と続いている。
転勤によって居住する場所が不安定になると、体の自由がきかない親の介護に支障をきたす。持ち家を持つことは難しくなるし、子どもにも度重なる転校などの負担を強いることになりかねない。年齢を重ねるに連れて、転勤への困難さは増していく傾向にある。
これらのリスクを回避するためには単身赴任を余儀なくされることもあり、多くのビジネスパーソンはここに不安を抱えているのではないだろうか。「結婚しづらい(29.3%)」もまた、転勤によって生じる今後のさまざまな困難を想定したうえで、結婚自体を躊躇う人がいることを示唆している。少子化問題が叫ばれる昨今、これはゆゆしき問題である。
転勤がある企業に対して「過去3年間で、転勤において家庭的事情等を考慮したことがあるか」をたずねたところ、最も多かったのは「親等の介護(56.7%)」であり、正社員が感じている困難のトップと一致していた。次点には「本人の病気(42.1%)」が続いており、介護とあわせて「やむを得ない事情」と判断されているようだ。
しかし、「正社員が困難に感じること」で2位(68.1%)となった「持ち家の購入」について、企業の配慮は9.4%という低い数値を示しており、重視されていないことがわかる。また、「子の就学・受験」に対する配慮は22.2%、「出産・育児」は28.2%、「結婚」は23.8%と、「持ち家の購入」よりは高い数値であるものの、7割以上の企業で「子どもや結婚に関すること」に対する配慮が成されていないと考えると、ビジネスパーソンが結婚や出産に踏み切れないのも無理はない。
転勤は企業独自の経営判断に基づいて行われるもので、企業人である以上、業種や企業の企業によっては、転勤と無縁でいられないというビジネスパーソンは多い。しかし、転勤が個人の生活に及ぼすさまざまな問題について、軽視することはできない。ワークライフバランス型のワーカーや、共働きの核家族が増えてきているという、現代人のライフスタイルの変化に、企業が対応できていない現状がある。
これまでは、転勤の可能性がある企業に正社員(総合職)として就職した以上、転勤命令は余程の事情がない限り受け入れなければならないという価値観が主流だった。転勤をしたくなければ、転勤のない企業に就職するか、「勤務地限定正社員」といった雇用形態を選ぶしかなかった。しかし同調査において、勤務地限定正社員の雇用区分がある企業は15.8%に留まっている。
さらに、勤務地限定正社員と全国転勤型との間の年収差(給与・賞与含む)について、27.4%の企業が「5~10%未満」、25.3%の企業が「10~15%未満」という割合で「ある」と回答している。実際には同じ内容の仕事をしていても、全国転勤型の社員は会社にとって融通がきく分、限定社員よりも優遇されて然るべきであるという意識が根強い。転勤しない=収入が下がる・キャリアアップのチャンスが減る、といった公式が成立してしまっているのだ。
しかし今、ここに新たな動きが出てきている。AIG損害保険株式会社が、2019年4月より「望まぬ転勤」を廃止すると発表し、新卒応募が10倍になったことで話題になった。ワークライフバランスが重要視される昨今、これまでは「企業命令」として絶対であった「転勤」に対する見直しもまた、働き方改革の一環として取り組むべきことなのかもしれない。
企業側から提示される「転勤あり」という条件に対して、「断ったら採用してもらえない」、「出世のためにはやむを得ない」等の理由で、しぶしぶ転勤を了承している人も多い。また、入社当初は特に困難を感じていなくても、年齢を重ねて人生のさまざまな岐路に直面したときに、状況が変わることもある。転勤は「命令」によって決定するのではなく、その都度企業と社員の対話によって慎重に進められることが望ましい。
企業目線で見れば「融通が利く人材」へのニーズが高いのは必然であるが、ICT・IoTやAIなどの技術が進む社会においては、人を動かさずに仕事を進める手段が増えていくことも期待される。ビジネスパーソンのキャパシティや価値観が過去とは大きく変化してきている昨今、企業側には最新鋭の技術を取り入れた業務変革も求められてきているのではないだろうか。