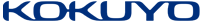仕事のプロ
2017.02.13
大塚グループ各社元社長大塚正士氏のトップとしての決断〈後編〉
チャンスを転機に変えることで誕生した世界に誇る陶板名画美術館

昭和48年に起きたオイルショックは、高度経済成長を続けてきた日本経済を一変させる出来事だった。建設業界も同様で、高層ビル建設に使用する大型タイルを開発したばかりの大塚オーミ陶業株式会社は、いきなり経営危機に直面する。良い商品をつくっても物が売れなければ経営は成り立たない。この危機を脱するために、大塚正士社長が目をつけたのが「美術陶板」。この発想の転換が会社の危機を救い、やがて世界に誇る陶板名画美術館である「大塚国際美術館」の設立へとつながっていく。
大塚国際美術館に込められた思い
大塚グループ創立75周年事業として設立された大塚国際美術館。他にも周年事業の構想はあったが、なぜ美術館を選んだのか。ビジネスとはかけ離れた存在である美術館建設には、大塚社長の地元、鳴門に対する想いがあった。
「当初の構想では、大阪本社ビルの改築、広告宣伝館の建設も予定していましたが、バブル崩壊の影響もあり、また、大塚社長の『長年、大塚が徳島県にお世話になったお礼に、75周年事業として地元に恩返しがしたい。また世界のどこにもなく、いつまでも残るものをつくりたい』という強い想いもあったため、美術館建設だけに絞りました。
この時期、本州と四国を高速道路でつなぐ明石海峡大橋が開通する頃で、鳴門が素通りされないよう、人の流れを止めるダムの役割として美術館を建てれば、観光資源が少ない鳴門に多くの観光客が集まり、にぎわう。大塚社長は、地元鳴門を盛り上げていこうと考えていました」
大塚国際美術館に展示されている作品数は、西洋の絵画を中心に1075点。これは、大塚社長が美術館構想を打ち出した時から言い続けていた、1000点以上の絵画を展示するという強い意志によるものである。大塚国際美術館には、作品以外にもいたるところにこだわりが詰まっている。
「美術館構想から建設、完成までに数多くの課題が山積みでした。特に海外の美術館に美術陶板の技術力の高さを伝え、複製の許可をもらうのにかなりの時間を要したと聞いています。また許可をもらった後も、世界の名画の複製を制作するにあたり、オリジナルを忠実に再現するための現地調査や厳しい検品など、ハ-ドルを乗り越え、気が付けは構想から完成まで10年ぐらいかかっていました。この10年で何回も現地に足を運び、交渉や調査を繰り返したスタッフの努力は並大抵ではありません」
「また、陶板名画は原画を原寸大で再現したものですが、額はできるだけ現地と同じものを作り、光の当たり具合も現地の環境に合わせて設計しています。この美術館は、構想に携わった人たちの想いやこだわりが随所に詰まっています。
美術館の総工費は、75周年ということで、75億円で計画していました。6名の美術の専門家に依頼して、作品の選定から配置などいろいろ相談しましたが、専門家も今までにないことで夢が膨らみ、あれも展示したい、これも展示したいとなって、最終的に400億円かかりました。ただ、1000点以上の作品はもちろん、美術館すべてに大塚グループの技術が結集しています」
世界25か国、190以上の美術館が所蔵する至宝の西洋名画1000点以上を、大塚オーミ陶業の特殊技術により、オリジナル作品と同じ大きさに再現し、原画の芸術的価値を日本にいながら体感することができる大塚国際美術館は、大塚グループの技術や想いが詰まったショールームとも言える。美術陶板は、褪色劣化していくオリジナル作品と異なり、2000年以上にわたり、そのままの色を残し、文化財の記録保存にも貢献するものである。今では、陶板名画美術館として、世界中から高い評価を受けている。
人々の暮らしを支える商品を開発してきた大塚グループにとって、美術陶板は生活に直接関係していない商品ではある。しかし、なかなか見ることのできない西洋の名画を日本で気軽に見られる大塚国際美術館は、美術を通して人々の心を豊かにしている。大塚グループは、これからも人々の生活を支え、心を豊かにする事業に挑戦していく。
大塚国際美術館(OTSUKA MUSEUM OF ART)
大塚国際美術館は、日本に居ながらにして世界の美術を体感できる「陶板名画美術館」です。古代から現代に至る、西洋美術史を代表する名画1,000余点を、陶板で原寸大に再現し、展示しています。約4㎞におよぶ鑑賞ルートには、レオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』、ゴッホ『ヒマワリ』、ピカソ『ゲルニカ』など、美術書などで一度は見たことがあるような名画を一堂に展示しており、世界の美術館を味わうことができます。